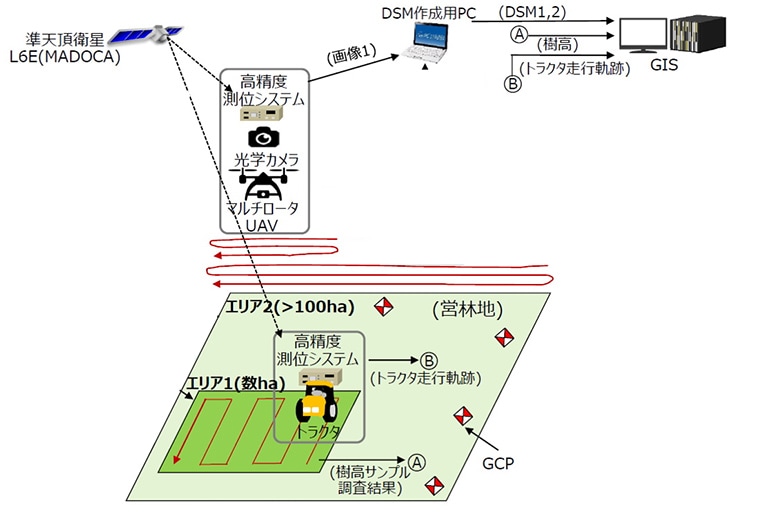MHPが、こうした技術の開発に取り組む理由は、植林地全体の蓄積量を緻密かつ高精度に把握することで、植林にまつわる一連のプロセスの最適化を進め、供給能力を高めることができるからです。
これによって、バイオマス・エネルギーなど製紙用パルプ以外の分野にも木材を供給し、事業の発展を図ろうとしています。ここで蓄積量の計測が重要な役割を担う理由について、MHPのトップを務める桑原卓也さん(取材当時)は次のように語っています。
「植林事業において生産性を高める上で重要なポイントは、『見える化』と『高精度化』。つまり、蓄積量をきめ細かく把握し、さらにその精度を高めることです。これらによって改善すべき課題が浮き上がってきます」(桑原さん)