京都大学卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科(MBA)修了。鉄鋼メーカー、文教大学などを経て現職。経営情報学会会長、国際CIO学会副会長(同学会誌編集長)、CRM協議会顧問、英ハル大学客員研究員、米カリフォルニア大学バークレー校客員研究員などを歴任。メーカーでの経営企画職など、約10年の実務経験を持つ。経営情報学会論文賞を3回受賞。
日立の組織風土を変えたLumadaが持つ可能性とは ~Lumadaが照らす協創による未来~ 後編

オンライン化やリモートワークの導入など、新型コロナウイルスの影響でデジタル化が加速しています。なかでもデジタル技術を活用して、業務やビジネスモデルを変革するDX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性が高まっています。
このDXを進める上で注目されているのが、日立製作所が提供するプラットフォーム「Lumada」です。前編に続き、後編ではLumadaの強みや具体的なユースケース、さらにはDXを成功させるポイントについて、早稲田大学ビジネススクール教授の根来龍之さんと日立製作所の高木順一朗さんの対談を通して探っていきます。
Lumadaの源泉となる「IT×OT×プロダクト」
根来:日立の強みは現場部門を持っていることだと思います。いわゆるITだけじゃなくてOT(Operational Technology)、つまり電力、産業、鉄道など、さまざまな現場で使われる機器をいかに制御、コントロールするかのノウハウや知識も併せ持っているということです。
最近、“Software Eats Everything”――、つまりソフトウェアがすべてを制御するという言葉をよく耳にします。確かに一部の家電やスマートフォンでは、どこのメーカーが作ったハードウェアでも、ソフトウェアが同じように制御できる世界がある。でも工場設備や社会インフラのような複雑な世界では必ずしもそうはならない。
例えば、建設機械は油圧で動いていますが、ソフトウェアがいくら優れていても、3mmや5mmといったバルブやシリンダの動きは、時間をかけて蓄積したモノづくりの技術やノウハウがなければ制御できません。自動運転の対象となるクルマも同じです。
これから数十年先まで、産業機器の制御において「個別性」がある程度は残る。一方で、現場からのデータを基に価値を創出するIT領域では、業務効率化のために「共通性」も重要になってくる。だからLumadaのような「個別性」と「共通性」を併せ持つプラットフォームが必要であり、優れたサービスを現場に提供するためには、現場の知見とデジタルの知見の両方が不可欠なのだと思います。
高木:そう言っていただけるのは本当に嬉しいですね。われわれはよく「IT×OT×プロダクトによる価値創出」と呼んでいますが、日立にはエネルギー、インダストリー、モビリティー、ライフといった各種社会インフラの制御技術にITのデジタル技術やプロダクトを融合したユースケースやソリューションが豊富にあります。そのノウハウをLumadaで再利用できるのは、他社にはない大きな強みだと考えています。
Lumadaを活用した具体的なユースケースとは

根来:Lumadaのユースケースとは、顧客との協創で新たな価値を創出したデジタルソリューションをモデル化したものだと認識しています。横展開できるソリューションのテンプレートが、どのような課題解決のためにどう作られ、どのような成果を出したのか、教えていただけますか。
高木:製造業のお客さまから特に引き合いが多いのが、工場のIoT化による高効率生産への転換やサプライチェーンの最適化です。これらのユースケースの代表例となるのが、大手工作機械メーカーであるオークマとの協創です。
テーマとなったのは、工場での約4,000品目の超多品種少量生産の確立でした。Lumadaの「生産計画最適化ソリューション」を適用し、リアルタイムな部品搬送の作業指示を可能とする「工程管理システム」や、生産の進捗状況や設備の稼働状況を一元的に分析・可視化できる「進捗・稼働状況監視システム」を共同開発しました。
これにより、これまで「日」単位だった作業指示が「時・分」単位で行えるようになり、生産リードタイムを短縮したほか、ボトルネックを特定し、対策することを可能にしました。その後も両社の協創による成果をサプライチェーン全体に広げていく取り組みが進められています。
根来:日立自身が製造業ということもあり、現場の機器やシステムを動かす制御技術、ライン全体を高度化する生産技術、さらにはサプライチェーンも含めた全体最適化のノウハウには長年の実績があるんだと思います。それがLumadaには存分に生かされているわけですね。それでは、製造業以外でのユースケースはどのようなものがありますか。高木:コロナ禍では、社会インフラの設備保全や製品検査などでも、業務の効率化やリモート化が求められています。こうしたニーズに対応するのが、遠隔地の設備故障や製品不良を異常音や状態などから自動検知するソリューションです。これを活用すれば、リモートでの設備監視や品質管理などが容易に行えるようになります。
このほかに、日本マイクロソフトと協創したオフィスビルや商業ビル向けのソリューションである「BuilMirai(ビルミライ)」があります。都心部のビルではテナント企業の獲得競争が激化する一方で、新型コロナウイルスの影響による働き方改革が加速し、ビルの管理業務の効率化などが強く求められています。
BuilMiraiは、複数のビルにおけるエレベーターや空調設備などの稼働状況を遠隔で統合的に監視・分析できます。さらに、「人流データ」によりビル利用者の状況を把握できるため、効率的な清掃や警備に加え、エリアごとの混雑度を踏まえた管理が可能となります。
根来:BuilMiraiの記事を先日拝見しましたが、まさに「IT×OT×プロダクト」を体現したソリューションだと思いました。ビル全体の制御について考えると、「エレベーターや空調・照明設備をどう作り、どう制御するか」、「ビルの利用状況に合わせて人やセキュリティの管理をどう変化させていくか」など、ITだけじゃなくOTやモノづくりの知見も密接に関係してきます。
これを1社が持つリソースだけで対応することは難しい。だから他社も積極的に巻き込んで、ソリューションの拡充やグローバル展開を加速させていく。戦略的にも非常に興味深い事例だと思います。
DXを成功させるためには

根来:ところでLumadaを使ってDXを成功させるには、どのような工夫が必要でしょうか。実績あるソリューションが豊富に揃っていたとしても、自社の課題解決にそのままポンと生かせるかどうかはわかりませんよね。
高木:まず重要なのは、一足飛びにDXを進めようとするのではなく、できる範囲から改善を積み上げていくことだと思います。例えば、まだ生産実績の「見える化」さえできていないのに、いきなり生産工程の最適化ソリューションを導入しても、うまくはいかないということです。そこで日立は独自に策定した「Maturity Model(成熟度モデル)」をベースに、DXに向けた成熟レベルを着実にステップアップさせていくことを提案しています。
もう1つ重要なのが「協創」のアプローチです。DXに取り組むためには、自社にどのような課題があるのか、それをどう変えたいのかという明確な目標がなければ先に進めません。しかし、本質的な課題をきちんと把握している企業は、実は決して多くはありません。
根来:どの企業もさまざまな課題を抱えていますが、業務の役割や立場によって認識がかなり異なってくるからですね。それには、自分たちでも気づいていない「本質的な課題は何か」「どうしてこの課題が存在するのか」「解決への道筋は何か」「最終的にどのようなゴールをめざすのか」を、現場や経営層も含めたステークホルダー全員で議論し、明確化していく必要がありますね。
高木:その通りです。そこでLumadaでは、そうした協創を推進するための方法論として「NEXPERIENCE」を提供しています。具体的には、ステークホルダー全員を集めた「協創ワークショップ」を開催し、デザインシンキングのスキルを備えた日立の専門家がファシリテーターとなって、参加者が自由に意見やアイデアを出し合い、納得感を持ったゴールに向かって主体的に取り組めるようにしています。
また、新たに創出されるビジネスモデルやサービスが、利用者にとって本当に有用か、投資対効果や事業利益がどれほど望めるかなど、事業価値を事前に検証できるシミュレーターを活用し、デジタルソリューションの創造を支援しているのです。
根来:最新テクノロジーやシステムだけでなく、そうした顧客課題の抽出や意識改革などを丁寧に支援する体制も確立している点が、Lumadaの大きな強みなのだと思います。
しかし、ニューノーマルでは、業務プロセスの改善やサプライチェーンの最適化だけでは、市場変化に対応できない課題が山ほど出てくる可能性があります。例えば、クルマの自動運転が実用化されればシェアリングエコノミーによる交通システムが普及し、「自家用車を売る」というビジネス自体が大きく変わるかもしれない。それは生産ラインの改善とは全く別の問題になると思います。
高木:それはわれわれも実感しています。コロナ禍で国内外のサプライチェーンのあり方が大きく変化したように、お客さまが提供する製品・サービスも変革を迫られるかもしれません。日立はそういった変化を睨みながら、よりダイナミックで幅広い経営課題にリーチしていくことが求められていくでしょう。Lumadaでやるべきことは、まだまだたくさんあります。
Lumadaをグローバルに展開
根来:ところで、Lumadaが顧客のビジネスを革新してきたのと同様に、Lumadaという事業は日立自身の変革も促してきたのではないでしょうか。
高木:確かにLumadaという事業を始めて以来、従業員の意識や組織風土が大きく変わりました。ずっと「プロダクトアウト」だった発想が「マーケットイン」になり、プロダクトという形だけではなく、サービスやソリューションとしてお客さまに価値提供していくことが当たり前になりました。
また、日立単独でやりたがる主義だったのが、他社との“協創主義”に変わりました。事業部ごとの垣根も低くなり、スマートシティやMaaS(Mobility as a Service)といった組織横断型の案件に“One Hitachi”として取り組むことが多くなっています。
根来:以前の日立は、社内でさまざまな事業ドメインが棲み分けられていて、製品開発やノウハウも別々だったのだと想像します。しかし、Lumadaという事業は、一定の共通基盤を作っていく考え方なので、当然社内でも分野の垣根が取り払われていくことになるのだと思います。
つまり複数の事業ドメインの集合体だった会社が、ドメイン間を貫く共通基盤を持つ会社に変わっていった。それがいまの日立なのではないかと思います。そうした意識変革やDXの成果について、Lumadaを通じて顧客企業に広げるとともに、グローバルでも存在感を示していくことが、今後の重要なテーマになるのではないでしょうか。
高木:ご指摘の通りです。国内はともかく海外における日立の「社会イノベーション事業」やLumadaの認知度と実績は、まだまだ低いと思っています。しかし、ニーズはどの国でも共通する部分が多いはずなので、今後は世界中の企業の課題解決や人々のQOL(生活の質)向上にLumadaで貢献していきたいと考えています。
根来:日立は日本という国の産業全体を代表する、数少ない企業の1つです。世界的にもさらに発展し、新しい世界を切り拓いてほしいです。大いに期待しています。
根来 龍之 早稲田大学ビジネススクール教授
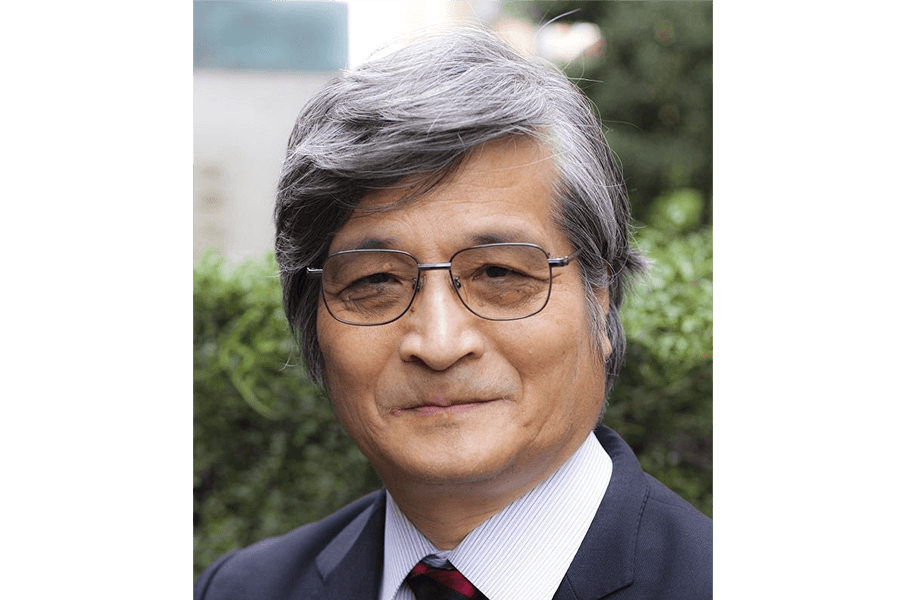
高木 順一朗
日立製作所
アプリケーションクラウドサービス事業部 本部長
1998年日立製作所入社。入社後は、一貫してITのソフトウェア畑を歩み、企業向けミドルウェア製品から組込みソフトウェア、また各種クラウドサービスを国内、海外問わず展開。2016年のLumada発足後は、クラウド上でお客さまのDXを加速する様々なLumadaソリューションと、その基盤となるサービスプラットフォームの事業運営に携わる。2021年4月からは、社会システム事業部で電力会社向けの各種エネルギーシステム事業を管掌する。

Lumada Innovation Hub
 デジタルで社会にイノベーションを。
デジタルで社会にイノベーションを。ここから一緒に。
詳細はこちら







