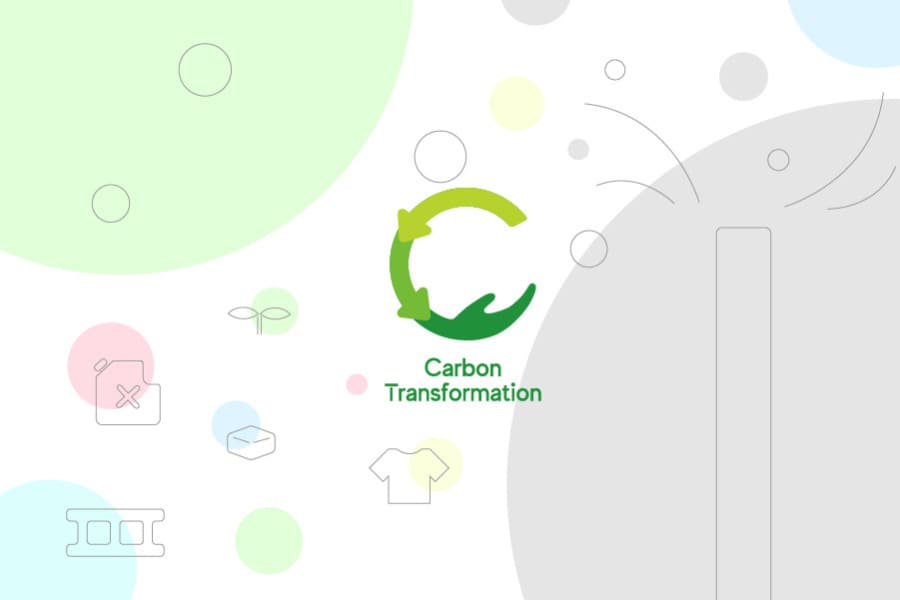企業からの注目高まる「DEI」とは? わかりやすく解説
日立と南極~地球の最果てで発電を60年間支え~

霞に包まれた海の氷を割いて渡ると、突然と現れる岩場の大地。地平線に臨むのは真っ白な氷床。夏なのに肌を刺すような風にも、心地良さを覚える。まるで漫画のような別世界に来た──日立製作所の田端志野さん(31)は、国立極地研究所に出向し、第65次南極地域観測隊の隊員として、2023年12月、南極に降り立ちました。
さかのぼること1956年、日本は第1次南極地域観測隊を派遣し、観測事業を開始しました。南極は、人間の活動による環境汚染が最も少ない地域の一つで、その気象や地層データを観測し分析することで、地球の自然環境や環境問題を解明しようとする試みでした。観測は繰り返され、オゾンホールの発見やオーロラの発生の仕組みが判明するなど、大きな成果が上がっています。
では、日立製作所に入社した一介の会社員の田端さんが、どうして観測隊に参加し、南極に降り立つことになったのでしょうか?それを知るためには歴史をひもとく必要があります。
日立と南極の歴史は、イギリスの人気ロックバンド・ビートルズが来日して日本中が沸いていた1966年、茨城県日立市の工場から始まりました。

始まりは突然の辞令
「早く帰ってこい」。多賀正昭さん(84)は1966年2月、大阪府出張の真っただ中にも関わらず、勤めていた日立市の工場に急に呼び戻されました。何が何だか分からないながらも、工場へ夜に戻ってみると、待ち受けていたのは「とにかくついて来い」という上司の一言。次に向かったのは、所属していた部門の副部長の社宅でした。笑顔で出迎えた副部長からは酒を振舞われ、さらに不思議に思いました。夕食もご馳走になりながら、「山岳部で山が好きだから、寒い所も得意だろうか?」と聞かれたことのみ印象的でした。
翌日に出勤して「北海道へ異動かな」と考えていると、また上司から「ついて来い」の一言。一緒について行くと、今度は副工場長の執務室です。部屋へ入ると、副工場長から辞令が発せられました。「南極に行ってもらう」。全く想像していなかったからか、多賀さんは「学科試験はありますか?」とすっとんきょうな質問します。部屋がどっと笑いに包み込まれました。
観測のためだけでなく、極寒の地で生きていくためにも、南極では電気で色々な機器を動かさないといけません。日本が南極に建てた昭和基地の生命となる電力は、持ち込んだ発電機によって供給されていました。発電機から生じた電力を設備や機械に分配する配電盤や機械をコントロールする制御盤も含めてメンテナンスが必要で、その製造を手掛ける日立製作所の社員に白羽の矢が立ったのです。
多賀さんは当時26歳で、設備の管理やメンテナンスを担当するチームの一員として、第8次南極地域観測隊(1966年)に参加し、昭和基地に向かいました。
南極で待ち受けていたのは、容量が小さい発電機2基でした。しかも、そのうちの1基、20kVA発電機は故障しており、残る1基、40kVA発電機のみで生活と観測の両方の電力を賄っていました。当時は南極に持って行けた設備も多くはありません。大事な1基だったので、多賀さんは持ち込んだ工具で、観測用のみの電源として使えるよう修理しました。

その後、発電機にまつわる他のトラブルも発生します。航海中の荒波で、運んできた燃料に海水が混ざっていると発覚して大騒ぎに。異常の検知も担う制御盤の検査を工場で担当していた知識を生かして、発電機に送られる燃料に水が混ざっているか検知する警報装置を取り付け、観測隊を支えました。
基地から離れ、「冒険」へ
多賀さんの後には、後輩たちが続きます。日立製作所で発電機の検査を担当していた滝川清さん(74)が、第16次隊(1974年)として南極に赴きます。
今回も昭和基地の発電機や付帯する設備のメンテナンスが役割でしたが、発電機が安定していたこともあり、南極に滞在した間の3分の1の期間、計116日間、基地から離れ観測旅行に繰り出しました。「未開の地を冒険していくような心境でした」と滝川さんは話します。観測旅行は、目標物もない真っ白な世界への旅路です。方位を知るための磁石も正確に作動せず、一定の方角を向かないことがあります。隊員たちは慎重に進んでいきます。

旅の仲間は6人の隊員で、学者、医者などそれぞれが専門家。観測旅行中は滝川さんを含めても7人しかいないので、何でも協力し合います。滝川さんは、学者の風よけに何分も立って、測量機器が揺れないように支援しました。「食料を分けたり、見張りを立てたり、支え合いながらの冒険でした」と振り返ります。

ああそれ行けどんと行け発電機
未開の地での大冒険から、温水洗浄便座など、文明の利器が活用できるようになったのは、第24次隊(1983年)~第26次隊(1985年)の設営部門(機械)の隊員たちの尽力によるものです。3年間で200kVA×3基の発電機を設置しました。日立製作所から第26次隊に選抜され、設置に携わった渡邊敏浩さん(63)は、3基の重要性を強調しました。1基を動かし、1基をバックアップとして確保することで、残り1基を整備できるため、昭和基地の生活に最も重要な電気を常に途切れないよう継続した運転ができるようになったといいます。

また発電容量も向上したことから、観測隊員たちの生活は大きく改善されました。最低限の生活用水のために、雪や氷を少量しか溶かせませんでしたが、容量の大きい発電機が放出する大量の熱を利用して、風呂に入れる量の水を確保するのに成功しました。昭和基地の他の隊員たちもその喜びを、隊員たちが自作して毎日発行する昭和基地新聞で表現しています。「あっというまに灯がともる これが日立の発電機 ああそれ行けどんと行け 発電機」と昭和基地音頭の第6節でたたえました。
先達からのバトン
前編の本記事では、日立の社員が観測隊に参加するきっかけや、観測隊の黎明期から発電を支えてきた歴史を振り返ってきました。その振り返りもまだまだ20年強。先達からのバトンはさらに受け継がれていきます。日立から国立極地研究所への出向、南極での悪戦苦闘は続いていくのです。後編「隕石、ペンギン、停電、それぞれの南極の日々」では、バトンを受け取った各世代の隊員たちを紹介していきます。